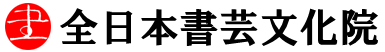書道歳時記~桜の話
土屋彩明
(新潟県見附市)
前回までの記事で小学生~中学生くらいの方向けの話題が一段落したので、これからしばらくは季節の話題などを取り上げようと思います。
タイトルは「書道歳時記」としました。
歳時記(さいじき)というのは俳句に使う季語を集めて季節ごとに分類した本のこと。
私は特に俳句を作る訳ではないのですが、歳時記は興味深い解説や綺麗な写真がついている物も多く、読んでいて楽しいので時々図書館で借りてきます。
ああいうテンションで、季節ごとの書道や手書き文字文化、漢字や日本語についての話題を取り上げてみたいと思います。
今回は春らしく「桜」について調べてきました。
意外なことに「さくら」の語源ははっきりとは分かっておらず、いくつか説があるのだそうです。
面白いので、今回本で見かけた説をまとめてみました。
- 「咲く」に複数形の「等(ら)」を付けて「サクラ」となった
- 古くは「咲く」ことを「サカユル」と言い、この名詞系「サカユラ」が転じて「サクラ」となった
- 「サ」は早苗の田の神、「クラ」は神様の御座所(帝の玉座「高御座(たかみくら)」と同じ「クラ」)という意味で、春に農耕の神が降り立つ花という意味合いで「サクラ」となった
この他にもまだ説があるようです。
桜の歌は万葉集にも数十首あるそうで、古くから愛された花だからこそ様々な話があるのでしょうね。
ちなみに私は中学生の頃に古典の授業で「平安時代の歌や文章で単純に『花』という時は桜を指す。それより古い時代は梅を指した」と習いました。
なので『源氏物語』で祖母が若紫の幼さを語るシーンで「この子は難波津(なにわづ)の続け書きがようやくできるようになったばかりで」と出てくる「難波津=難波津に咲くやこの花冬ごもり 今を春べと咲くやこの花」という歌を長いこと桜の歌だと思っていたのですが、これはもっと古い時代に作られた歌で「花」は梅を指すそうです。
この歌は平安時代当時は手習い(文字の練習)によく書かれた歌だそうで、当時の人たちは「花=桜」という共通認識を持ちつつ、この梅の歌を書き継いでいたのはちょっと面白いなあと思います。
もう一つ個人的に好きな花の歌「花の色は移りにけりないたづらに わが身世にふるながめせしまに」という、百人一首にも入っている小野小町の歌は、平安時代の歌なので素直に桜と解釈して良いようです。